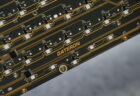おすすめゲーミングキーボード|60種類以上を徹底比較

この記事ではおすすめのゲーミングキーボードを紹介します。
おすすめゲーミングキーボード 比較表
* 最新の情報に更新するよう努めていますが、既にファームウェアのアップデートにより性能が向上している可能性があります
| 製品名 |
 |
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||
| 評価 |
5.0 out of 5.0 stars
|
5.0 out of 5.0 stars
|
5.0 out of 5.0 stars
|
4.5 out of 5.0 stars
|
4.5 out of 5.0 stars
|
| キー配列 | ANSI / ISO | ANSI | JIS / ANSI | JIS / ANSI | JIS / ANSI |
| サイズ | 60% | 75% | TKL | Full / TKL / 60% | TKL |
| AP |
0.1 ~ 4.0mm
0.1mm単位で調整可
|
0.4 ~ 3.6mm |
0.1 ~ 3.0mm
0.1mm単位で調整可
|
0.2 ~ 3.8mm | 1.0mm |
| キーストローク | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 3.8mm | 3.2mm |
| Rapid Trigger | 対応 0.15 ~ 2.35mm | 対応 0.2mm | 対応 0.1 ~ 2.5mm | 対応予定 | 非対応 |
| キースイッチ | Lekker Switch | Magnetic Switch | 東プレスイッチ | OmniPoint | Corsair OPX |
| スイッチ特性 | 磁気 / リニア | 磁気 / リニア | 静電容量 / ソフトタクタイル | 磁気 / リニア | 光学 / リニア |
| 押下圧 | 40cN – 60cN | 35gf – 55~60gf | 45g / 30g | 45cN | 45g |
| ポーリングレート | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 8000Hz |
| 商品リンク |
おすすめゲーミングキーボード Q&A
- Q. 最もコスパが高いキーボードは?
-
到着までの日数や価格の安さを重視するならDrunkDeer A75がおすすめです。1万円台でRapid Triggerやアクチュエーションポイント調整機能を搭載しています。
- Q. VALORANTのストッピングがしやすいキーボードは?
-
Wooting 60 HEやREALFORCE GX1、DrunkDeer A75はRapid Trigger機能を搭載しており、VALORANTでのキー離しストッピングの速度や精度を高めます。
- Q. 遅延が少ないゲーミングキーボードは?
-
Corsair K70 RGB TKL OPXやCorsair K60 PRO TKL OPXは光学式スイッチ搭載、ポーリングレート8000Hzにも対応しており、トップクラスに遅延が少ないです。
- Q. カスタマイズ性の高いキーボードは?
-
Wooting 60 HEやDrunkDeer A75などホットスワップ対応(はんだ付け無しでキースイッチを取り外せる)キーボードはカスタマイズしやすいです。キースイッチに潤滑剤を塗るルブをはじめとするMODによって打鍵感や打鍵音を改善できます。Wootingは互換性のある60%ケースなら換装できるので、見た目のフルカスタマイズが可能です。
- Q. Rapid Triggerの違いは体感できる?
-
Rapid Triggerによる違いはすぐに体感できます。キーを離した瞬間にオフになり、再度押し込んだ瞬間にオンになるので、より直感的なキー操作が可能になります。
Rapid Triggerについて詳しく知りたい方はこのページをご覧ください。
- Q. WootingとDrunkDeerのRapid Triggerを比較すると?
-
執筆時点では、Wooting 60 HEは最短0.1mm、DrunkDeer A75は最短0.2mmでの設定が可能です。Wooting 60 HEを1年以上使用して慣れ切った状態でDrunkDeer A75を検証しましたが、この0.1ミリの差はそこまで大きいと感じませんでした。VALORANTは普段とほぼ同じ感覚でプレイでき、唯一キャラクターを左右に切り返しながらタップ撃ちをするときなど、細かなキャラクターコントロール時にわずかな差が出るように感じました。
- Q. 4000Hzや8000Hzポーリングレートの違いは?
-
ポーリングレートとは1秒間あたりにPCへ情報を送信する回数を表します。例えばポーリングレートが1000Hzなら、1秒間に1000回、言い換えると1ms(1ミリ秒)ごとにPCへ情報を送信します。
ポーリングレートを高く設定するメリットは、キーの入力情報を検知する回数が増えるので、遅延が少なくなることです。「違いを体感できるか」と質問されることが多いですが、わずか数msの差なので体感するのは難しいでしょう。
注意点として、ポーリングレートを高く設定するとPC(主にCPU)への負荷も大きくなります。PCスペックには余裕を持たせておいた方が良いでしょう。
おすすめのゲーミングキーボードの中で、Corsair K70 RGB TKL OPX、Corsair K60 PRO TKL OPXは 8000Hz ポーリングレートに対応しています。
ゲーミングキーボード おすすめ5選

| キー配列 | ANSI / ISO | サイズ | 60% |
|---|---|---|---|
| アクチュエーションポイント |
0.1 ~ 4.0mm
0.1mm単位で調整可
|
キーストローク | 4.0mm |
| Rapid Trigger | 対応 0.15 ~ 2.35mm | 機能名称 | Rapid Trigger |
| キースイッチ | Lekker Switch | スイッチ特性 | 磁気 / リニア |
| 押下圧 | 40cN – 60cN | ポーリングレート | 1000Hz |
高性能かつカスタマイズ性に優れたゲーミングキーボード
今流行りのRapid Trigger機能を初めて搭載したゲーミングキーボード。Rapid TriggerはVALORANTやCS2の基礎技術「ストッピング」を移動キーを離して行う際の速度や精度を明らかに向上させるので、たびたびPay to winキーボードとも言われています。また、アクチュエーションポイントも0.1mm ~ 4.0mmの間で0.1mm単位で調整できるので、逆キーでのストッピング速度向上にも貢献します。
60%キーボードはキー数が不足しがちで、普段使いとの併用は慣れが必要ですが、Wooting 60 HEは1つのキーに2種類の割り当てが行えるMod Tapという機能により弱点を克服します。例えば左上のEscキーに対して、短く押したときは半角/全角、長押ししたときはEscのように設定できます。これにより元のキー配列を変えないまま頻繁に使用するキーを追加することができます。
カスタマイズ性の高さも魅力の一つです。ケースはネジ5本で着脱可能、自分で用意した互換性のある60%ケースに換装できます。もちろんキーキャップやケーブルも交換可能。ホットスワップ対応で、さまざまなキー荷重のキースイッチが展開されているので、自分好みのキーの軽さを追求できます。
さらにこだわる方はキースイッチに潤滑剤を塗るルブや、MODなどの打鍵感を向上させるカスタマイズにも取り組んでいます。Wooting 60 HEの入手がキッカケでこういったカスタマイズに手を出す方も多いです。筆者がカスタマイズしたWooting 60 HEもかなり手を加えています。
到着までに長い時間が掛かることは人によっては難点と言えます。海外公式サイトでのみ販売されており、送料や関税を考えると費用は合計33,000円ほど掛かります。注文完了から到着までに1ヵ月~2ヵ月を要する状態が続いています。

| キー配列 | ANSI | サイズ | 75% |
|---|---|---|---|
| アクチュエーションポイント | 0.4 ~ 3.6mm | キーストローク | 4.0mm |
| Rapid Trigger | 対応 0.2mm | 機能名称 | Rapid Trigger |
| キースイッチ | Magnestic Switch | スイッチ特性 | 磁気 / リニア |
| 押下圧 | 35gf – 55~60gf | ポーリングレート | 1000Hz |
安価で入手できるRapid Trigger搭載ゲーミングキーボード
最前線のスペックながら2万円以下で入手できるゲーミングキーボードです。なるべく費用を掛けずにアクチュエーションポイント調整機能やRapid Trigger機能を体験したい方にお勧めです。
DrunkDeer A75に搭載されているRapid Trigger機能は最短0.2mmで設定できます。他のRapid Trigger搭載機との0.1mmの差がありますが、実際にVALORANTをプレイしていて、普段の感覚でキー離しストッピングしても大きな違いを感じませんでした。細かな差まで追求したい人なら話は別ですが、0.1mmのような細かい数値の差よりもRapid Triggerの有無のほうが明らかに重要な気がします。
英語配列、人気の高い75%レイアウトであることも特長の一つです。F1~F12や矢印キーが搭載されており、60%と比べて普段使いでも困りづらいのは利点です。
Wooting 60 HEと比べて注文から到着までに掛かる日数が短く、価格も安いので、入手性やコストパフォーマンスを重視する方におすすめ。公式サイトからの注文時にクーポンコード mioni を入力すると20%オフで購入できます。

| キー配列 | JIS / ANSI | サイズ | TKL |
|---|---|---|---|
| アクチュエーションポイント |
0.1 ~ 3.0mm
0.1mm単位で調整可
|
キーストローク | 4.0mm |
| Rapid Trigger | 対応 0.1 ~ 2.5mm | 機能名称 | Dynamic Mode |
| キースイッチ | 東プレスイッチ | スイッチ特性 | 静電容量 / ソフトタクタイル |
| 押下圧 | 2種類から選択可 45g / 30g | ポーリングレート | 1000Hz |
トップクラスの機能性を誇る国産ゲーミングキーボード
日本語配列と英語配列の2種類から選択できる、東プレ独自の静電容量無接点キースイッチを搭載した国産テンキーレスゲーミングキーボード。
先日のファームウェアアップデートでRapid Trigger機能(Dynamic Modeと呼称)が追加されました。他のRapid Trigger搭載キーボードよりも細かな調整にも対応しているのが長所となります。オンとオフの距離を個別に調整でき、それぞれのキーに異なる数値を設定することも可能です。
静電容量無接点方式を採用した東プレスイッチはソフトなキータッチが特徴です。押し始めの感触がとても柔らかく、キーの跳ね返りも弱めです。打鍵音もかなり小さいです。Wooting 60 HEやDrunkDeer A75に搭載されている磁気キースイッチや、その他キーボードに搭載されるメカニカルキースイッチとは打鍵感が大きく異なることには注意が必要です。
キー荷重は30gと45gの2種類から選択できます。押下圧30gモデルはタクタイル感をほぼ感じませんが、とにかくキーが軽いので注意。常に脱力した状態で操作する人に適しています。押下圧45gモデルは柔らかくて大きなタクタイル感があり、キーを押すとタクタイル感とともに一気に底の付近まで降りていきます。キーを押した感触が欲しい方に適しています。

| キー配列 | JIS / ANSI | サイズ | Full / TKL / 60% |
|---|---|---|---|
| アクチュエーションポイント |
0.2 ~ 3.8mm
0.1mm単位で調整可
|
キーストローク | 3.8mm |
| Rapid Trigger | 今夏にアップデートで対応予定 | 機能名称 | Hyper Trigger |
| キースイッチ | OmniPoint | スイッチ特性 | 磁気 / リニア |
| 押下圧 | 45cN | ポーリングレート | 1000Hz |
大型アップデートを控える人気ゲーミングキーボード
アクチュエーションポイントを最短0.1mmに調整できる機能を搭載していることで人気を博したSteelSeries Apex Proシリーズですが、既に今夏のファームウェアアップデートでRapid Triggerに対応することがアナウンスされています(SteelSeriesはHyper Triggerと呼称)。今のところ機能の詳細は不明ですが、日本正規代理店が運用するSteelSeries公式Twitterでは「競合製品に対して”上位互換になる”予定」と強気の発言もあり、たびたび注目を集めています。
他の機種とは異なり、Apex Pro Mini Wirelessなどのワイヤレスモデルも展開しているのが魅力です。また、2023年モデルが新たに登場してから、旧製品のApex Pro TKL USが19,000円台まで値下がりするなど、2022年以前のモデルがお得に購入できます。Apex Proシリーズ内すべての過去製品に対して上記のアップデートが適用されることも発表済みです。
日本語配列と英語配列の両方を展開し、フルサイズからテンキーレス・60%などレイアウトも様々なので、求めている条件に合った機種を見つけられるかもしれません。

| キー配列 | JIS / ANSI | サイズ | TKL |
|---|---|---|---|
| アクチュエーションポイント | 1.0mm | キーストローク | 3.2mm |
| Rapid Trigger | 非対応 | 機能名称 | – |
| キースイッチ | Corsair OPX | スイッチ特性 | 光学 / リニア |
| 押下圧 | 45cg | ポーリングレート | 8000Hz |
超低遅延・トップクラスの反応性を誇るゲーミングキーボード
流行りのRapid Trigger機能は不要と考えていて、反応速度が最速クラスのゲーミングキーボードを探している方にお勧めです。特長は光学式スイッチ搭載とポーリングレート8000Hz対応の2つです。
光学式スイッチの利点は、遅延が少ないことと、チャタリングが発生しないこと。一般的なメカニカルキーボードでは、スイッチの二重入力を防ぐためにデバウンスタイムと呼ばれる遅延をあえて設けています。光学式スイッチの検知方法ではデバウンスタイムが0でもキーが二重に入力されることはないので、その分メカニカルキーボードよりも遅延を抑えられます。
ポーリングレート8000Hzで動作させると、1秒間に8000回、通常のキーボードの8倍もの頻度でキーの入力状況を検知するので、これまた遅延が抑えられます。光学式スイッチと8000Hzの組み合わせは、極めて遅延が少なくなり、トップクラスの応答性をもたらします。高ポーリングレートでの動作はPC(主にCPU)に負荷が掛かるので、PCスペックには余裕を持たせておく必要があります。
メディアキーを搭載するモデル K70 RGB TKL OPX も展開しています。
ゲーミングキーボードの売れ筋ランキング
Amazon.co.jpと楽天市場の売れ筋ランキングで、人気のゲーミングキーボードをチェックしましょう。国内ではLogicool(ロジクール)やSteelSeries(スティールシリーズ)、Corsair(コルセア)、Razer(レイザー)が人気なようです。
ゲーミングキーボードのティアーリストを見る
ゲーミングキーボードのティアーリストはこちらのページで見れます。
最後に
今回はおすすめのゲーミングキーボードを紹介しました。この記事がキーボード選びの少しの助けになれば嬉しいです。より詳細なレビューを読みたい方は新メディア Gear MetriX をチェックしてください。
また、筆者はゲーミングデバイス データベースも作成中なので、よければ目を通してみてください。